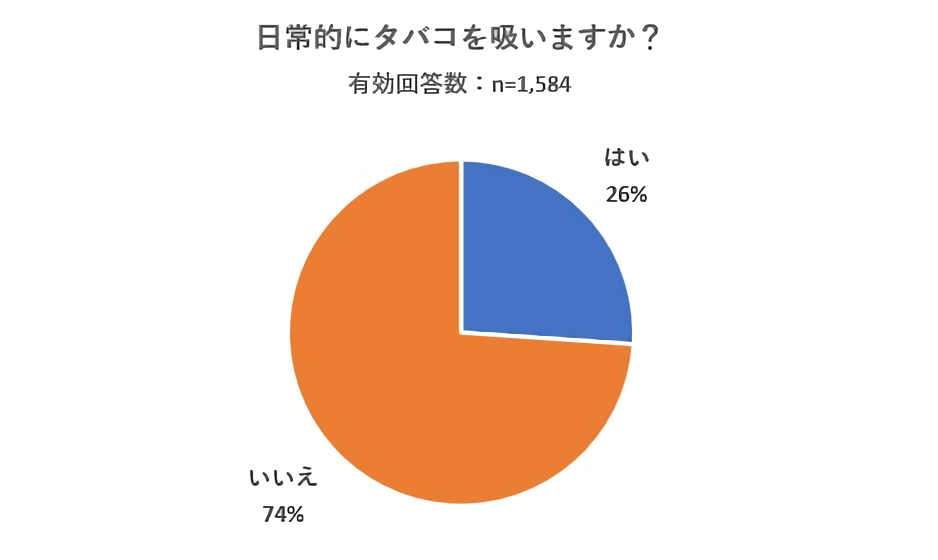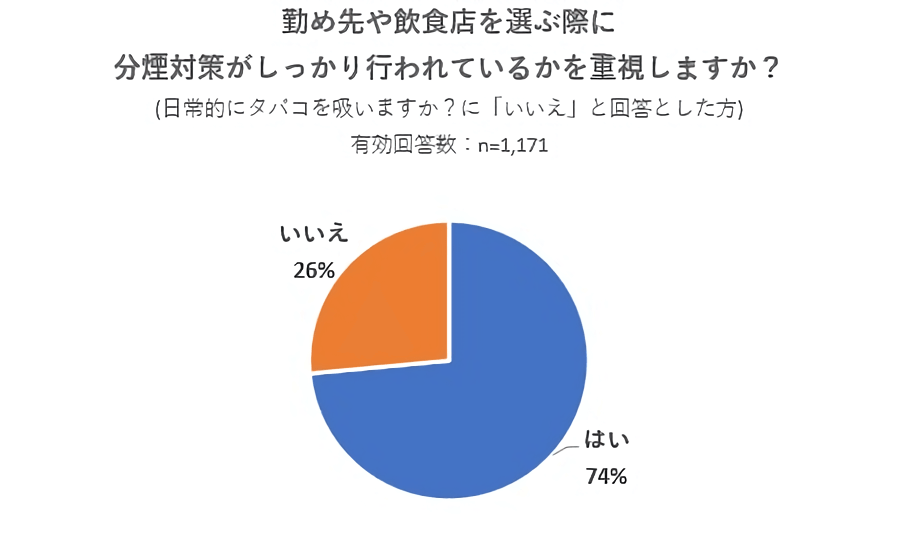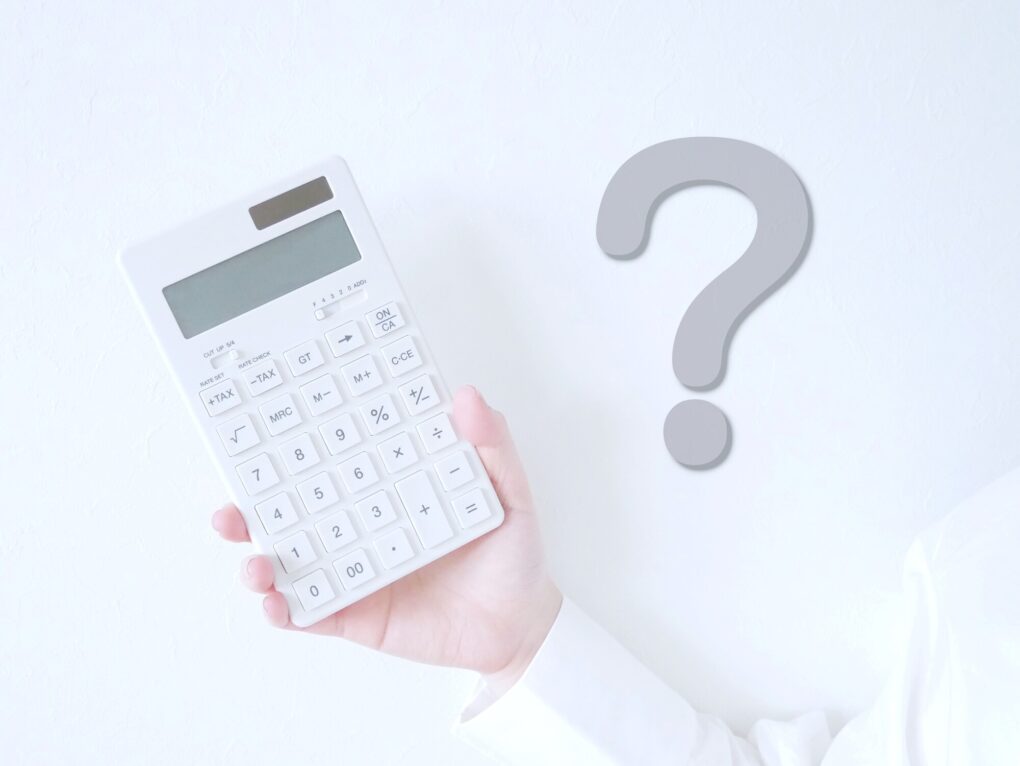おすすめ喫煙(分煙)ブース比較一覧
おすすめの喫煙(分煙)ブースランキング
リピート利用多数!有名企業や飲食店、ホテルなど幅広く選ばれている喫煙ブース
スモーククリアは、㈱エルゴジャパンが提供している高性能喫煙ブースです。きれいな気流を生み出すファンと給気口、
また一回のろ過で有害物質とニオイを取り除く最高性能フィルターにより快適な空間が実現しています。
もちろん厚生労働省の3つの技術的基準もオールクリア、1回のろ過で有害物質とニオイを取り除ける機能を持つ高性能フィルターのH14HEPAフィルター(ヨーロッパ規格最高クラス)を搭載しています。そのためダクト工事も不要で導入のハードルも低く、すでにオフィスや飲食店など5,000台以上の導入実績があります。初期費用0円のレンタルプランもあり、導入費用を抑えたい方にもおすすめです。
| 会社名 | 株式会社エルゴジャパン |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング7F |
| TEL | 050-3627-4605 |
| TVOC除去率 | 99%以上 |
| 消費電力 | 2人用内部排気約170W |
| サイズ | W820×D970×H2,000㎜~W1,590×D1,650×H2,110mm |
| ダクト接続 | 可能・不要 |
スモーククリア(㈱エルゴジャパン)の詳細情報
費用
レンタルプラン初期費用0円/月額3万9,800円
(税込4万3,780円)~ 販売価格はお問合せ
性能
ニオイを外に漏らさない給気口
ニオイを服や髪に付けさせない脱臭性能
ニオイを感じさせない高性能フィルター
※境界面風速:0.2~0.3m/s、
浮遊粉じん:0~0.006mg/m³、
TVOC除去率:99%以上
設置場所
ダクト工事不要でテナント〜 地下まですべての場所に簡単設置
屋外設置の場合は、お問い合わせください。
最小0.5 帖のスペースから設置可能
導入事例
-
事例①ホテルマイステイズ金沢片町

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア/空気清浄BOX 使用人数 – 設置施設 ホテル -
事例②ひらゆの森

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア 使用人数 4人用 設置施設 温泉旅館 -
事例③ホテルサンバレー富士見

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア 使用人数 4人用×2台 設置施設 ホテル -
事例④御やど清水屋

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア 使用人数 4人用 設置施設 温泉旅館 -
事例⑤三翠園

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア 使用人数 4人用 設置施設 温泉旅館 -
事例⑥ホテルニューニシノ

引用元URL:https://www.ergojapan.co.jp商品名 スモーククリア 使用人数 2人用 設置施設 ホテル
商品紹介
| 使用人数 | 1人 |
|---|---|
| 外径寸法 | 縦タイプ:W820×D970×H 2,000mm 横タイプ:W970×D820×H 2,000mm |
| 内径寸法 | 縦タイプ:W770×D640mm 横タイプ:W620×D790mm |
| 使用人数 | 2人 |
|---|---|
| 外径寸法 | W1,590×D1,350×H2,110mm |
| 内径寸法 | W1,540×D1,000㎜ |
- スモーククリア(㈱エルゴジャパン)の詳細情報はこちら
-
導入実績5,000台以上!スモーククリア(㈱エルゴジャパン)の公式サイトはこちら
吸う人も吸わない人も快適な空間分煙を実現したスタイリッシュな喫煙ブース
スモークポイントは、㈱Fujitakaが提供する北欧独自のスタイリッシュさが特徴の喫煙ブースです。デザインだけではなく品質においてもしっかりとした設計がされており、喫煙テーブルだけでは不可能な空間分煙を実現します。
喫煙室に必要な基準もクリアしており、ダクト工事が不要なためテナントでも設置が可能です。また分解して再度設営が可能なので、店舗移動などにも対応できるでしょう。
| 会社名 | 株式会社Fujitaka |
| 住所 | 京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F |
| TEL | 0120-533771 |
| TVOC除去率 | 95%以上 |
| 消費電力 | 1~3名用約560W |
| サイズ | W820×D920×H2,200~W2,000×D1,720×H2,200 |
| ダクト接続 | 可能・不要 |
スモークポイント(㈱Fujitaka)の詳細情報
費用
レンタルプラン 月額7万円~
性能
揮発性有機化合物(TVOC)の除去率95%以上、廃棄粉じん量は0.015mg/㎥まで除去
導入事例
従来製品を大きく超えた煙・タバコ粒子除去率を可能にした最先端喫煙ブース
クリーンエア(クリーンエア・スカンジナビア㈱)の分煙キャビンは、屋内で100V電源があればどこでも設置できる喫煙ブースです。捕集が困難とされるたばこ粒子をほぼ100%捕集できる設計で、快適な空気環境を実現します。
提供はレンタルのみとなっており、利用人数に応じた提案をしてくれるので最適なブースが設置できるでしょう。定期的なメンテナンスにも対応してくれるので、社員の負担もありません。
| 会社名 | クリーンエア・スカンジナビア株式会社 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター10F |
| TEL | 03-6274-6385 |
| TVOC除去率 | 95%以上 |
| 消費電力 | 2人用 省エネモード 105W/通常速度 240W (電力定格) |
| サイズ | W1,200×D1,000×H2,170~W2,850×D1,410×H2,170 |
| ダクト接続 | 記載なし |
クリーンエア(クリーンエア・スカンジナビア㈱)の詳細情報
費用
利用人数に応じて提案
性能
捕集が困難とされるタバコ粒子をほぼ100%捕集
導入事例
安心の無料設置相談と設置後の改善提案まで行う厚労省に認められた喫煙ブース
トルネックスは、㈱トルネックスが提案する喫煙ブースです。屋内空間に設置しても周囲の受動喫煙を抑制することができる環境配慮型の喫煙ブースで、1人用のコンパクトサイズから展開しています。
また分煙に関する相談を無料で受け付けているのも魅力。相談から喫煙室に必要な機器の設置工事、分煙機のメンテナンス、喫煙室の改善提案までワンストップで対応してくれます。
| 会社 | 株式会社トルネックス |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小舟町6-6 小倉ビル |
| TEL | 03-5643-5800 |
| TVOC除去率 | 95%以上 |
| 消費電力 | 1人用35W・4人用約165W/220W |
| サイズ | W820×D1000×H2195mm~W4685×D1800×H2720mm |
| ダクト接続 | 可能・不要 |
トルネックス(㈱トルネックス)の詳細情報
費用
オープン価格
性能
厚生労働省の分煙効果判定基準や、神奈川県受動喫煙防止条例などの法令基準にも配慮した設計
導入事例

引用元:ワンパス(JGコーポレーション)公式サイト
https://www.sanikleen.co.jp/bunen/solution/onepass/
厚労省の基準を満たす高い性能と場所を選ばず簡単に設置可能な喫煙ブース
ワンパスはJGコーポレーションが提案する、脱煙機能付きの喫煙ブースです。脱臭機は臭有毒ガスに反応する多孔質吸着材を採用し、化学吸着により再飛散することなく確実に脱臭してくれるため臭いを気にする場所でも安心です。
また設置する場所によって排気ダクトの接続を背面や側面にする、高さを変更するなどにも柔軟に対応。100V電源がある場所なら、どこにでも設置することができます。
| 会社 | JGコーポレーション |
| 住所 | 東京都港区港南2-12-26 港南パークビル7F |
| TEL | 03-3276-7271 |
| TVOC除去率 | 95%以上 |
| 消費電力 | 470W 定格風量時 |
| サイズ | 1〜7人 1.66〜3.79m² |
| ダクト接続 | 可能・不要 |
ワンパス(JGコーポレーション)の詳細情報
費用
未掲載
性能
無段階変速ファンを利用し、フィルターやダクトの汚れによる機内外の圧力損失に追従できる性能
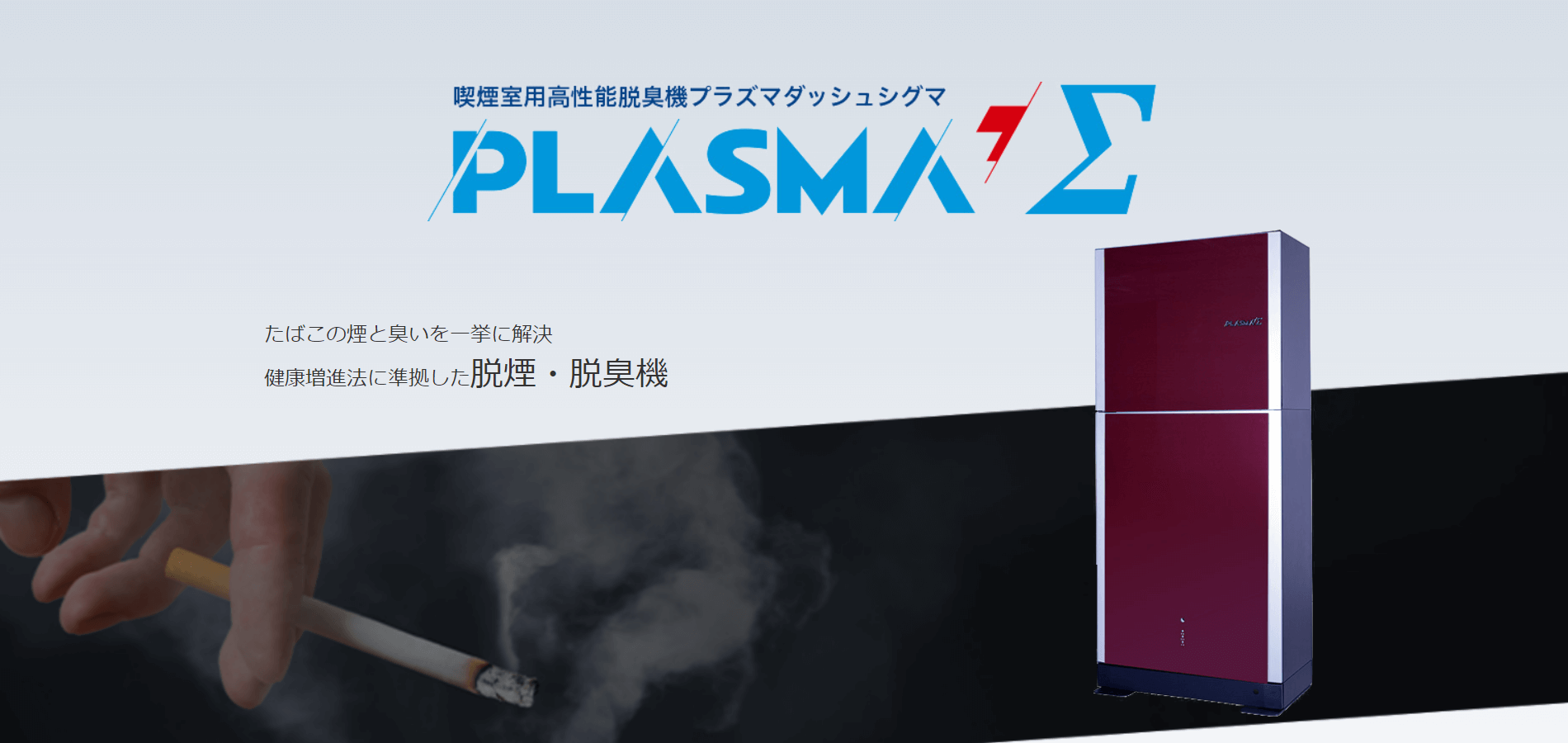
引用元:プラズマダッシュ(日鉄鉱業㈱)公式サイト
https://www.nittetsukou.co.jp/kikai/product/plasmasigma/index.html
場所を問わず簡単に設置可能、従来製品の脱臭機能を大幅に超えた喫煙ブース
プラズマダッシュは、日鉄鉱業㈱が提案する喫煙ブースです。プラズマ脱臭技術搭載で、従来の分煙機では除去できなかった、たばこの臭いを大幅に低減してくれます。また本体が空気清浄機と排気機構を兼ねているので、屋外排気が難しい場所への設置もできます。
コンパクトサイズやスリムサイズもあり、設置する場所の状況に合わせて選べるのも嬉しいポイント。さまざまなシーンでたばこのにおい「無臭化」を実現してくれます。
| 会社 | 日鉄鉱業株式会社 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号(郵船ビル6F) |
| TEL | 03-3284-0516(代表) |
| TVOC除去率 | 95%以上 |
| 消費電力 | 100W~500W |
| サイズ | W600×D348mm×H1,105~W800×D450mm×H2,000 |
| ダクト接続 | 不要 |
プラズマダッシュ(日鉄鉱業㈱)の詳細情報
費用
プラズマダッシュシグマ本体価格(参考):165万円(運搬・設置費別)
性能
処理した空気を屋内(喫煙空間外)へ排気可能。本体が空気浄化と排気機構を兼ねている
喫煙(分煙)ブース一覧紹介
菱熱工業株式会社が販売している組立式分煙装置は、1人用の省スペース設計の喫煙ブースです。簡単な組み立て式であり、循環タイプや排気接続タイプ、高性能フィルター循環タイプなどのさまざまなタイプが用意されています。
| 住所 | 〒143-0025 東京都大田区南馬込2丁目29-17 |
|---|---|
| TEL | 03-3778-2111 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 設置後でも上部ユニットを取り換えることでさまざまなタイプに変更可能 |
喫煙ブース(株式会社フレッシュタウン)
株式会社フレッシュタウンの喫煙ブースは、30年以上の実績のある企業です。レンタル喫煙ブースの提供として、イベントや展示会の制作なども総合的に手掛けるサービスも提供可能です。
| 住所 | 〒134-0091 東京都江戸川区船堀7-2-8 |
|---|---|
| TEL | 03-3804-2525 |
| 費用 | ■PXシリーズ 室内喫煙室(レンタル):38万円~ ■FXシリーズ 屋外喫煙所(レンタル・販売・リース):【レンタル価格】19万円~/【販売価格】106万円~ ■PXシリーズ 室内喫煙所(販売・リース):【販売価格】42万円~ ■喫煙用集塵・脱臭機(レンタル・販売):26万円~ |
| 性能 | 厚生労働省・東京都助成金対応可 |
アイリスオーヤマ株式会社の喫煙ブースは、屋内用、屋外用の喫煙ブースを提供しており、内装工事が不要なユニット式となっています。1人から2人用のブースから6人、7人用の大型ブースまで用意されています。軽量でありながらしっかりとした強度を持ち、改正健康増進法に対応しています。
| 住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命クレアタワー19階 |
|---|---|
| TEL | 0120-990-860 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 「改正健康増進法」に対応 |
アイピック株式会社の喫煙ブースは、「施工型パーテーション」であるため、今あるスペースを活用して喫煙ブースを自由設計することができます。またメーカー直販であるため、業界トップクラスである相場価格の50%も実現させています。
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-5 ユニゾ岩本町3丁目ビル2F |
|---|---|
| TEL | 0120-020-720 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 価格が安く、フルオーダーで作れる |
エコスモーキングは、煙が漏れない設計となっており完全腰個室の喫煙ブースとなっています。屋内でも屋外でも設置可能で、容易な組み立て式のコンパクト設計です。
また業界最小サイズの引き戸タイプを採用しているため、さまざまな空間に設置することができます。
| 住所 | 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田1-16-2 ガーデンヒルズフォー102 |
|---|---|
| TEL | 048-915-3656 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 完全な個室空間なので煙が外に漏れず、オプションパーツによって拡張可能 |
SMAAT分煙ブースは、3密を回避するスマートデザインとなっており、2人分の利用で抑える小型の分煙ブースとなっています。スピード換気も特徴となっており、たったの30秒で空気の入れ替えが可能です。
| 住所 | 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 |
|---|---|
| TEL | 04-2951-1660 |
| 費用 | 198万円(税込) |
| 性能 | 協力スピード換気により常に新鮮な空気を保つ |
pureda boxは、最小タイプの喫煙ブースであり、1人から2人用となっています。また一定時間を過ぎると電源がオフになるため、無人のときにはしっかりと省エネもできます。
またたばこの煙や匂いがブース外に逃げないエアカーテンが出入口となっている点も特徴のひとつです。
| 住所 | 〒111-0035 東京都台東区西浅草2-4-5 |
|---|---|
| TEL | 03-5604-5959 |
| 費用 | 100~500万円 |
| 性能 | 天井部のエアクリーナーが活性炭フィルターによって有害物質を99%除去 |
りらっくハウスND 喫煙タイプ(タカノ株式会社)
タカノ株式会社が提供するりらっくハウスNDは、受動喫煙対策に簡単な設置と組み立てを可能にした屋外型喫煙ハウスです。大きな特徴として、工場での組み立て出荷と、ノックダウン(現地組み立て)式を選べることが挙げられます。
| 住所 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137 |
|---|---|
| TEL | 0265-85-3150 |
| 費用 | ■ND-A 基本タイプ(1型)【現地組立】:79万2,000円(税込) ■ND-B デッキタイプ(1型)【現地組立】:105万2,700円(税込) ■ND-C デッキタイプ(1型)【完成品出荷】:117万3,700円(税込)など |
| 性能 | スペース不要の引戸タイプ、出入口は側面設置も可能 |
スモーク&トーク(株式会社中村製作所)
スモーク&トークはドイツメーカーの製品を改良したものです。元のドイツモデルは、毎年優れたデザインの製品に送られる「IFデザイン賞」を2007年に受賞するなど、見た目のよさも認められています。
| 住所 | 〒271-0093 千葉県松戸市小山510番地 |
|---|---|
| TEL | 047-330-1112 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 吸引した空気中の粒子を約99.995%除去して排出 |
WISEの喫煙ブースは、ウイルス対策として利用者同士の接触と密を避けながら、ドアなしでも煙が外に漏れにくい設計で実現し、注目を集めています。コンパクトサイズなので場所を選ばず設置できること、既存施設に違和感なく溶け込むレイアウト、デザインを採用できることも魅力です。
| 住所 | 【東京OFFICE】〒102-0085 東京都千代田区六番町9-10 ロータス六番町203 |
|---|---|
| TEL | 022-205-4185 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 利用者数に合わせて適切な場所に設置できる |
G-SMOKING(サンマックス・テクノロジーズ株式会社)
G-SMOKINGという言葉をご存じですか?サンマックス・テクノロジーズ株式会社が開発して受動喫煙防止のための喫煙ブースです。近年禁煙や分煙が進んでいますが、どのような役割を果たしてくれるのでしょうか。今回は、G-SMOKINGの特徴や導入によって得られるメリットについて詳しく解説します。
| 住所 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号 古賀オールビル4F |
|---|---|
| TEL | 03-5652-1571 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 2~4名に対応の埋込換気扇を1台装備 |
かんたんダッシュシガーProは、活性炭脱臭のパイオニアが消臭技術を駆使して開発しており、喫煙室内部及びその周辺のたばこ臭90%以上の除去を実現しています。また、活性炭(ヨウ素炭)吸着技術と2台の脱臭装置(シガーPOT+Q-ポット)により、技術的経過措置基準をクリアしています。
| 住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野 6-23-5 第二雨宮ビル10階 |
|---|---|
| TEL | 03-5830-7951 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 90%以上の脱臭効率を実現 |
SMOXは、屋内外に対応可能な喫煙ブースとなっており、電話ボックスの型材をもとに制作しているため、頑丈な点も特徴です。15秒で中の空気を全部入れ替えができ、1人用の少人数向けのサイズも用意されています。
| 住所 | 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-1 |
|---|---|
| TEL | 0282-45-1341 |
| 費用 | 記載なし |
| 性能 | 15秒で空気の全入れ替えが可能 |
おすすめ喫煙(分煙)ブース比較一覧
| イメージ | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 |
| 会社名 | スモーククリア(㈱エルゴジャパン) | スモークポイント(㈱Fujitaka) | クリーンエア(クリーンエア・スカンジナビア㈱) | トルネックス(㈱トルネックス) | ワンパス(JGコーポレーション) | プラズマダッシュ(日鉄鉱業㈱) |
| 特徴 | 高性能で快適な空間! リーズナブルに導入できる | 北欧独特のスタイリッシュさを大切にした筐体デザイン | タバコの煙と臭いを完全に除去し、快適な空気環境を提供 | コンパクトで低価格な1人用ブースもあり | 柔軟なレイアウトが可能 | プラズマ脱臭技術を搭載 |
| 性能 | 境界面風速:0.2~0.3m/s、浮遊粉じん:0~0.006mg/m³、TVOC除去率:99%以上 | 揮発性有機化合物(TVOC)の除去率95%以上、廃棄粉じん量は0.015mg/㎥まで除去 | 捕集が困難とされるタバコ粒子をほぼ100%捕集 | 厚生労働省の分煙効果判定基準や、神奈川県受動喫煙防止条例などの法令基準にも配慮した設計 | 無段階変速ファンを利用し、フィルターやダクトの汚れによる機内外の圧力損失に追従できる性能 | 処理した空気を屋内(喫煙空間外)へ排気可能。本体が空気浄化と排気機構を兼ねている |
| 費用 | レンタルプラン初期費用0円/月額3万9,800円(税込4万3,780円)~ 販売価格はお問合せ | レンタルプラン 月額7万円~ | 利用人数に応じて提案 | オープン価格 | 未掲載 | プラズマダッシュシグマ本体価格(参考):165万円(運搬・設置費別) |
| メンテナンス | フィルター交換、出張修理サービス、一般清掃 ※買取プランの場合 | フィルターメンテナンスあり | サービス・スタッフが空気浄化フィルターと、タバコの吸殻を定期的に点検・交換 | メンテナンス契約によって定期メンテナンスあり | 衛生管理のプロ『サニクリーン』が、定期的に空気浄化フィルターの交換 | 不明 |
| お問い合わせ | 電話・メールフォーム | 電話・メールフォーム | 電話・メールフォーム | 電話・メールフォーム | 電話・メールフォーム | メールフォーム |
| 詳細リンク | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る |